こんにちは、カナちひ(@kana_chihi)です。
ブログ用の物撮りに、旅行先の風景、気が向いたときのスナップやポートレート。
僕の撮影スタイルはずっと、標準〜広角域がメインでした。
その点、望遠レンズは正直ちょっと遠い存在。
重そうだし、かさばるし、そもそも出番ある?なんて思っていたんですが、最近、子どもの学校行事や仲間内でのイベントで「もう少し寄れたらな」と感じる瞬間が、少しずつ増えてきて──
そんなとき出会ったのが、「FE 70-200mm F4 Macro G OSS II」。

解放F値がF4からという部分が気になって、購入前にレンタルしてみたんですが、使ってみるとそんな心配を忘れるくらい、ずっと身近で、楽しい。
何より“ちょっと先の世界”を撮れる望遠と、”リアルを見落とさない”マクロの組み合わせが、とても魅力的で、後日ソニーストアで購入しました。
今回はそんなソニーの純正望遠ズームレンズ「FE 70-200mm F4 Macro G OSS II」について作例や、使ってみた感想などを紹介します。
概要|普段使いできる望遠レンズ

FE 70-200mm F4 Macro G OSS IIは、ソニーEマウント用の中望遠〜望遠ズームレンズ。
大三元レンズ「FE 70-200mm F2.8 GM OSS II」と比べると開放F値は控えめですが、そのぶん軽量かつコンパクト。
にもかかわらず、描写力やAF性能はかなり本格的で、しっかり“Gレンズ”らしさを感じとれる仕上がりになっています。

さすがに標準ズームレンズほど万能ではないけど、はじめて望遠レンズを使ってみたい人や、軽さと性能のバランスを重視したい人にとっては、有力な選択肢になりそう。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 外観 |  |
| 対応マウント | ソニーEマウント(フルサイズ対応) |
| 焦点距離 | 70-200mm |
| 開放F値 | F4通し |
| 最短撮影距離 | 0.26m(ワイド端)/ 0.42m(テレ端) |
| 最大撮影倍率 | 0.5倍(ハーフマクロ) |
| フィルター径 | 72mm |
| 重量 | 約794g |
| 全長 | 約149mm(収納時) |
| 手ブレ補正 | 光学式(OSS) |
| AF駆動 | XDリニアモーター×4 |
| テレコン対応 | 1.4x / 2.0x テレコンバーター対応 |
| Check |
このレンズの大きな特徴のひとつが、ハーフマクロ(0.5倍)撮影に対応していること。
広角側で最短26cmまで寄ることができて、肉眼では捉えきれない小さな花や昆虫を大きく映し出してくれます。


マクロレンズまでは必要ないけど、もう少し寄れるといいな──そんなニーズにも寄り添えるズームレンズって実は結構貴重だったりします。
もうひとつ好印象だったのが、このサイズ感。

望遠ズームとしてはとても軽くて、コンパクト。
小さめのバッグに入れて持ち歩ける携帯性は、望遠レンズのハードルをグッと下げてくれます。
ただしズームは繰り出し式で、使用時は思ったより伸びる。ホコリも侵入しそうだし、バランスも大きく変わるので、ここは少し評価が分かれるところかも。
レビュー|使ってわかったこのレンズの魅力

寄れることって、とにかく楽しい
標準域のレンズだと、つい“撮れる範囲”で構図を組んでしまうんですが、このレンズを使って感じたのは、「今まで撮れなかった距離に、手が届く感覚」。
たとえば、こんな日本庭園の中で見かけた苔むした石灯籠や、水面にひっそり浮かぶ小島。


木漏れ日の下で静かに佇む日本家屋を、遠くからそっと切り取った一枚は、こちらの想像以上にシャープで、色も落ち着いた素敵なトーンに仕上がっていました。

あと、特に印象的だったのが、その“引き締まった描写”。
JPEG撮って出しでもすぐに使えるくらい自然で、細部の解像感も高く、あとから色編集する手間が必要ないほど見栄えがするんですよね。もちろん、四隅まで。


ポートレートも得意分野
いうまでもなく、ポートレートに最適とされる中望遠(85mmから135mmくらい)も守備範囲。
人物撮影って、相手に”緊張感を与えない自然な距離感”がとても大事なんですが、これくらいだとカメラの存在を意識させずに撮れるんですよね。
被写体がリラックスできて、ふとした瞬間の表情も捉えやすくなる。



正直F4だと「ボケ感は少し物足りない」と感じるシーンもなくは無いんですが、望遠側ではしっかり圧縮効果も感じられて、背景をふんわり、人物をスッと浮き上がる望遠レンズならではの表現が可能です。
いわゆる“盛れる”画角なので、これから人物撮影を始めたいという人にもぴったりだと思います。

暗所はすこしだけ工夫が必要
一番気になっていたのが、F4という絞り値。
結論、日中や屋外での撮影ではまったく問題なく、とろけるような背景とはいかないまでも、望遠によるボケ感と、引き寄せ効果によってちょうどいい感じの「作品感」が生まれます。
個人的には「軽さとのバランスで考えればこれで充分」と感じました。





ただし、夕方や屋内、特に高画素機との組み合わせでは、ISO感度を上げたときにノイズが気になる場面がかなり出てきます。
α7RVとの組み合わせでは、ISO800あたりから徐々に描写のザラつきが気になってくる印象。


高画素機特有の“暗所に弱い特性”ゆえの結果ではあるのですが、明るい単焦点レンズと比べると、やっぱり暗所には弱いです。

屋内での自然光撮影や、体育館でのスポーツ撮影をしたい場合は、もう少し高感度のカメラを組み合わせる必要がありそう。
カメラや機材との相性はそれなりにあるレンズだと思います。
動画でも”ちゃんと使える”機能性
今回、動画作例はないんですが、ファインダー越しに感じた手ブレ補正(OSS)の効き具合はかなり高め。
望遠域でもしっかりと画面が安定してくれるので、手持ちでも十分運用できそうです。

さらに、ピント移動時の画角変化──いわゆる「フォーカスブリージング」もほとんど感じられず、これは動画にも相当意識して設計されているなと。
重さ的にも、ミドルクラスのジンバルで対応可能な範囲なので「普段とは少し違う動画を撮りたい」ってときにも心強いです。
望遠域ではフォーカスが迷いやすいレンズも多い中、AFも非常に静かかつ速く、このスピード感と信頼性もこのレンズを選ぶときの、大きな安心材料だと思います。
それでもちょっと気になるところ

ここまでの流れで、このレンズに対する僕の心酔っぷりはなんとなくご理解いただけたかと思いますが、実は気になる点もちらほら。
20万円以上するレンズだからこそ、気になる点もちゃんと見えてきます。
軽くてもやっぱり望遠レンズ
FE 70-200mm F4 Macro G OSS IIは、同じ焦点距離を持つ望遠ズームレンズとしてはかなり軽量な部類。
| FE 70-20mm F4 Macro G OSS II | FE 70-200mm F2.8 GM OSS II | 70-200mm F2.8 DG DN | 70-180mm F/2.8 Di III VC VXD G2 | |
|---|---|---|---|---|
| 外観 |  |  |  |  |
| メーカー | SONY | SONY | Sigma | TAMRON |
| 焦点距離 | 70-200mm | 70-200mm | 70-200mm | 70-180mm |
| 解放F値 | F4 | F2.8 | F2.8 | F2.8 |
| 重量 | 794g | 1,045g | 1,335g | 855g |
| Check | Check | Check | Check |
| FE 70-20mm F4 Macro G OSS II | FE 70-200mm F2.8 GM OSS II | 70-200mm F2.8 DG DN | 70-180mm F/2.8 Di III VC VXD G2 | |
|---|---|---|---|---|
| 外観 |  |  |  |  |
| メーカー | SONY | SONY | Sigma | TAMRON |
| 焦点距離 | 70-200mm | 70-200mm | 70-200mm | 70-180mm |
| F値 | F4 | F2.8 | F2.8 | F2.8 |
| 重量 | 794g | 1,045g | 1,335g | 855g |
| Check | Check | Check | Check |
実際、カバンに入れていても「大三元」ほどの圧は感じませんし、取り回しの良さにもそれなりの魅力は感じます。

とはいえ、それでもやっぱり“望遠レンズ”。街歩きで長時間撮影していると、じわじわと腕や肩にきます。
特に普段軽量の標準ズームレンズ「TAMRON 28-75mm F/2.8 Di III VXD G2」をメインに使っているとその差は明確で、油断すると地味に体力を持っていかれます。

身近なものだと、1.5ℓのペットボトルを横に構えた感じに近いので、はじめての望遠に触れるという方はそんなイメージをしておくと、購入時のギャップが減るかも知れません。

繰り出し式ズームは一長一短
FE 70-200mm F4 Macro G OSS IIは、ズームすると鏡筒が前に伸びる「繰り出し式」構造。


これ自体は軽量化やコンパクト化の面でメリットも多いのですが、雨や砂埃の多い場所で使うときは「ホコリや水が入りそうだな…」という不安がどうしてもちらつきます。

それなりに高価なレンズなので、一年に一度くらいは点検・清掃に出したいところですが、それなりのコストになるし、内部にまで入ったチリは取り除くことはできません。
| コース | 対象製品 | サービス料金 |
|---|---|---|
| ベーシックコース | ボディ+レンズ | 3,300円(税込) |
| ライトコース | ボディ+レンズ | 11,000円(税込) |
| フルコース | ボディ | 9,900円(税込) |
| レンズ | 12,100円(税込) |
| コース | 対象製品 | サービス料金 |
|---|---|---|
| ベーシックコース | ボディ+レンズ | 3,300円(税込) |
| ライトコース | ボディ+レンズ | 11,000円(税込) |
| フルコース | ボディ | 9,900円(税込) |
| レンズ | 12,100円(税込) |
ただ、ズームロックスイッチが搭載されているのは嬉しいポイント。バッグから取り出すときや、移動中に勝手にレンズが伸びないのは運用上も助かりますね。

絞りリングがないのは少し残念
このレンズ、物理的な絞りリングがついていません。
カメラ側で操作できるので実用上は問題ないのですが、価格的にはあってもよかったのでは?と思ってしまいます。

特に動画撮影時などは、手元でダイレクトに操作できるほうが自然だし、普段から絞りリング付きのレンズを使っていると、つい手がリングの位置を探してしまうんですよね。
上位のF2.8 GM OSS IIとのバランスやサイズ感を考えると、仕方ない部分ですが、率直に残念に感じました。
このレンズがフィットするひと

「望遠って、ちょっと構えてしまう」──そんな人にこそ、試してみてほしいレンズ。
扱いやすさと性能のバランスが本当に絶妙で、僕のように「なんだ、もっと早く使えばよかったな」と感じる人もきっと多いはずです。
最後に実際に使ってみて「ここに刺さりそう」と思ったシチュエーションをいくつか挙げてみます。
イベントや行事で、失敗したくないとき

広い校庭の向こうにいる子どもの表情をしっかり捉えたい。
でもスマホや標準ズームではどうしても小さくしか写らなくて──僕自身そんな悔しい経験をなん度もしてきました。
でも200mmまでカバーできるFE 70-200mm F4 Macro G OSS IIなら大抵のロケーションはカバーできるし、ソニー独自の「全画素超解像ズーム」で、質感を残したままさらにズームも可能。
素早いAFで、一瞬の笑顔や真剣な表情も、ブレずにしっかり残してくれる安心感は何物にもかえがたいなあと僕は思います。
家族や友人の自然な笑顔を撮りたいとき
近づきすぎると緊張させてしまう。
でも少し距離を置くだけで、相手は驚くほどリラックスしてくれます。
FE 70-200mm F4 Macro G OSS IIは、そういう“ちょうどいい距離感”をつくるのが得意なレンズ。
普段撮られ慣れていない友人の結婚式や、家族との日常の一コマ──
カメラを意識させずそっとシャッターを切れば、自然な表情のまましっかり映像に残せます。
引き寄せ効果で、スマホとは一味違う「作品」に仕上げたい時にも最適。

旅先で、”あと一歩寄り”たいとき

たとえば、遠くの山肌にだけ差す夕陽。
神社の境内で、鳥居の奥に見える灯籠のシルエット。
“この距離、この角度で、この瞬間”をそのまま切り取りたい──そんな時にこそ、このレンズの真価が発揮されます。
70-200mmは、旅先でこそ生きてくる焦点距離で、レンズ交換をせずに“寄れる”というのは、想像以上の自由度を与えてくれます。
重ささえ妥協すれば、これ一本で大抵のシーンはカバーできるはずです。
持ち歩くハードルが高いと感じたとき
どれだけ写りやカバー範囲の広いレンズでも、「持ち歩きたくない」と感じてしまっては、宝の持ち腐れ。
重い望遠レンズを試してみて、「これを持って一日歩くのは無理かも」と思ったことがあるなら、もう一度だけFE 70-200mm F4 Macro G OSS IIを試してみて欲しいです。
バッグにも収まるサイズ感で、街歩きスナップや軽めのハイキングでも、ちゃんと最後まで撮影できる。ここが本当に大事なんです。
望遠レンズが、日常の一本に昇華された、そんな印象のレンズです。

撮るものの幅を広げたいとき

花のつぼみ、カフェのテーブルに置かれたグラス、雨上がりの葉っぱ。
そういう“目の前の小さなもの”に、ふとシャッターを向けてみたくなるときもありますよね。
ハーフマクロに対応したこのレンズなら、そんな何気ない被写体にもきちんと寄れて、ピント面はキリッと、背景はふんわり。
なんとなく撮ってみたくなったものが、ちゃんと作品になる。そんな感覚が確かにありました。
もっと本格的にマクロ撮影がしたくなったとき、2.0Xのテレコンバーターで等倍マクロまで対応できるのも安心ですよね
まとめ|”日常に寄り添う”望遠レンズ

「望遠レンズって、自分には縁がなさそう」──最初はそう思っていたんですが、実際に使ってみると、その考えはいい意味で裏切られました。
FE 70-200mm F4 Macro G OSS IIの、遠くの被写体を引き寄せる力、圧縮効果による印象的なポートレート、ハーフマクロで身の回りの小さなものを丁寧に切り取る楽しさ。

そして、それらすべてを無理のないサイズ感で持ち出せるという扱いやすさ。
もちろん、暗所での撮影やズーム構造など、気になるポイントもゼロではありません。でも、それを補って余りある魅力が、このレンズには詰まっていました。
望遠の世界にちょっとだけ足を踏み入れてみたい。そんな人にこそ、ぜひ一度手に取ってみてほしい一本。

「いきなり購入するのは…」というひとは、僕のようにまずレンタルから試してみても良いかも知れませんね。
\ ここから借りられます /
以上、カナちひ(@kana_chihi)でした。
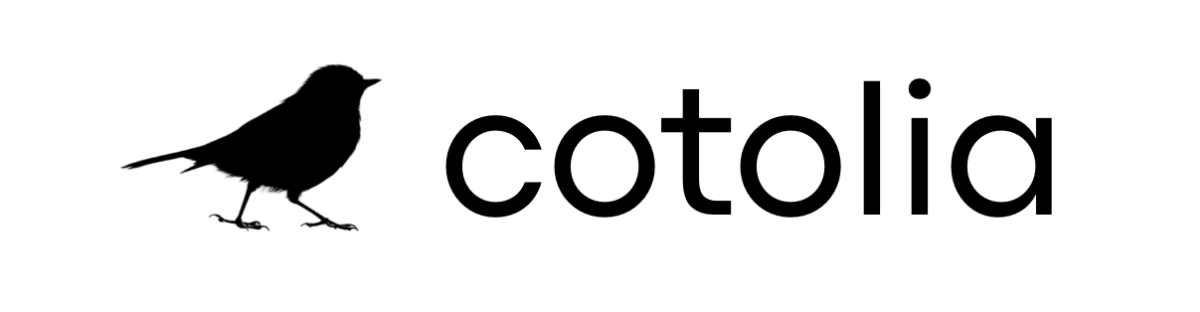




コメント